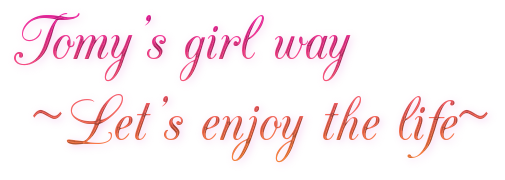【必見】これから簿記を勉強される方へ~①借方・貸方について~
2016/11/03
こんにちは、とみーです(*‘∀‘)
とみーは高校、専門と簿記の勉強をしてきたのですが、高校の頃はよくわからないまま授業を受けて、検定を受けてましたが、専門に通い、一日中簿記と向き合っている中で簿記は楽しい!!と感じるようになりました。
そこで、こちらのブログでこれから簿記の勉強をされる方や、現在勉強中の方のお役に立てたらなと思います(^o^)
借方・貸方の覚え方
簿記をしていく上でいつまでもいつまでもつきまとってくるのが勘定科目の仕訳で、仕訳をするには勘定科目を借方・貸方に分けなければなりませんよね。
貸借対照表の「貸借」という言葉のせいで左が貸方、右が借方とイメージしがちなので要注意です(; ・`д・´)
とみーは借方が左(かりかたの”り”が左はらい)、貸方が右(かしかたの”し”が右はらい)で覚えるんだよと高校生の頃の授業で習いました!
どっちがどっちかは分かっても、実際仕訳をする際どっちに仕分ければいいのかがわからないんですよね~( ;∀;)
そしてその悩みは、借方は資産の増加、負債の減少、費用の発生、貸方は資産の減少、負債の増加、収益の発生で覚えると良いと言われました(笑)
あたかも簡単さぁ!とでも言うように授業で再三言われていましたが、勘定科目もどれがどのカテゴリーになるのか覚えるまで仕訳も簡単でなかったです(-_-;)
それだけで簡単に仕訳けられたら苦労しないですよね(´・ω・`)
でも、日商簿記検定であれば解答用紙の貸借対照表等にあらかじめ勘定科目を書いてくれていることが多いので、それほど試験中に分からなくなって困る!!ってことはなかったです(笑)
勘定科目の覚え方について今回はさておき、、、借方・貸方についてはこんな感じで覚えてみてください(^^)/
仕訳をするうえで覚えておくべき2つの事!
1.借方・貸方のそれぞれの金額は一致する
どんな仕訳をする場合でも、借方と貸方の金額を一致させることが簿記のルールだと覚えてしまってください。
2.貸方・借方それぞれの勘定科目数は必ずしも同じだとは限らない。
借方と貸方の金額は必ず一致させることは簿記のルールと上記でお伝えしましたが、使用する勘定科目の数は異なる事もあるのでお気を付けくださいね(;''∀'')
★それでは、以上2点を踏まえて簡単な例を挙げてみましょう('◇')ゞ
【例①】商品100,000円を仕入れ全額現金で支払った。
| 借方 | 貸方 |
| 仕入 100,000 | 現金 100,000 |
【例②】商品300,000円を仕入れ現金で100,000円支払い残りを掛払いとした。
| 借方 | 貸方 |
| 仕入 300,000 | 現金 100,000 |
| 買掛金 200,000 |
と、まぁこんな感じです(^-^)
①も②も借方・貸方の合計金額は一致していますし、②では借方・貸方の勘定科目数は異なっています。
最後に・・・・
借方、貸方はどちらから仕訳けなければならないという決まりはありませんので、試験では問題を読んで度の勘定科目か分かる方から仕訳けてみてくださいね(^^)
ではでは今回はこの辺りで終わりとさせていただきます(^◇^)
ご精読ありがとうございました!
よろしければ、関連記事もどうぞ(∩´∀`)∩